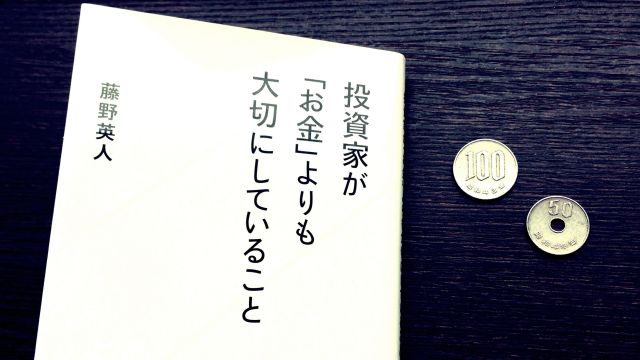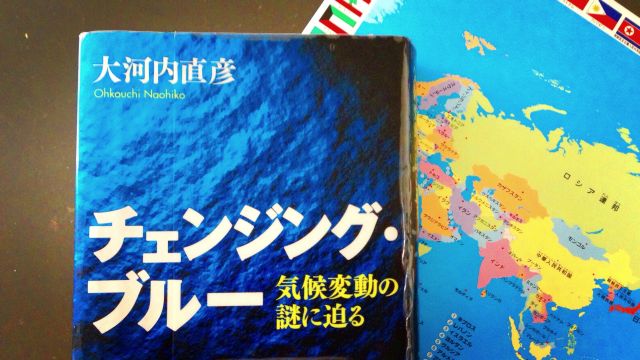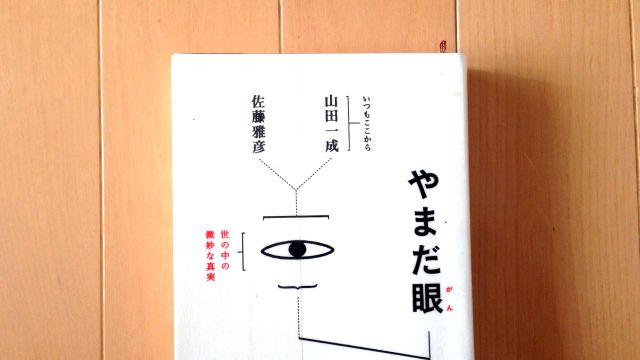ちょっと前ですけど、今年の本屋大賞は百田尚樹『海賊とよばれた男』になりましたね。出光興産の創業者・出光佐三をモデルにしたノンフィクション・ノベルです。
…で、そっちはまだ読んでなくてですね、今回ご紹介するのは藤野英人さんの『投資家が「お金」より大切にしていること』という新書です。藤野さんは出光興産の人というわけじゃなく、職業はファンドマネージャー。
この2冊がどう繋がるかというと、テレビ朝日系列で放映している『題名のない音楽会』なんです。
なにやら三題噺みたいですが、ちゃんと理由があります。
『投資家が~』は、投資家として20年のキャリアを持つ藤野さんが持つ、「お金とはなにか」を1冊に凝縮した本。藤野さんは読者にこう問いかける。
あなたには、「お金」より信じられるものがありますか?
あなたには、「お金」より大切なものがありますか?
あるよ、あるある、あるって。と反射的に返すのは簡単。でも実は「日本人は世界一ケチな民族」(=お金を信じている民族)だと第1章で藤田さんは説明する。
個人の資産は半分以上現金で、寄付を行う文化がない。それでいて、お金儲け=悪だと考えていて、お金持ちは悪い事をしていると考える。汗水たらして手に入れたお金しか信用しない。公のことは国がやるべきで、自分のお金で社会貢献をしようと考えない。でも増税はいや。
身も蓋もないなぁ…という感じだけど、確かに…という感触もある。トドメに持ってくるのはイソップ童話「アリとキリギリス」。アリのように真面目に働いて冬(ピンチ)に備えよう、という話だと思われがちだけど、実はそんな生易しい話じゃない。アリに見放されたキリギリスは、餓死してしまうのだ。
しかしこれ、いまの日本人の姿にそっくりではないでしょうか。
(中略)
日本人の、真面目に汗水たらして働くことが尊いという美徳は、反面的に、そういった働き方をしてない人間にた対して、牙を剥きます。
要は、遊んでいた人間は死んでもいい、というわけです。
でも、本当にそうなのでしょうか? (P75)
最近では生活保護に対する風当たりが強い。でも労働こそが価値ならば、お年寄りは?専業主婦は?生まれたての赤ちゃんは?
「人は、ただ生きているだけで価値がある」
勘違いしちゃいけないのは、藤野さんは「働いたら負け」と言ってるのではないんですよ。
「働く」にもいろいろあるし、「消費する」にもいろいろある。そのいろいろの中には「不真面目」なものがある。それはブラック企業だったり、衝動買いだったりする。形は変わるけれども、共通するのはお金に対して「不真面目」であるということ。
本当に暮らしを豊かにしたいと考え、幸せを求め、世界を善い方向にもっていく、そんな「真面目」なお金の使い道がある。「清貧」ではない、「清富」なお金というのがある。
藤野さんは言う。生まれたての赤ちゃんだって、オムツやミルクやベビーカーで、立派に経済を回している。社会貢献は、なにかを作り出すことだけでなく、消費することでも成し遂げられる。
人は、ただ生きているだけで価値がある。
『題名のない音楽会』という「投資」
そしてやっと冒頭の三題噺に戻ってきます。
改めて、『題名のない音楽会』はテレビ朝日系列で放映されているクラシック音楽を中心とした音楽番組。プリキュアを観てそのままにしておくと始まるアレです(日曜朝9時)
この『題名のない音楽会』はもうすぐ開始から50年になる長寿番組で、クラシック音楽をあつかう番組としては世界最長寿としてギネスに載っています。
そしてこの番組は、出光興産の一社提供なんです。開始からずっと。50年近く。
『題名のない音楽会』を一度でも観たことがある人はわかると思うんですけど、今時のテレビであんなに手間がかかっている番組って、そうそう無いんです。オーケストラを中心に、ホールにお客さんを入れて収録しているんです。テーマ決め、曲決め、オーケストラへのオファー、曲の練習、当日のリハーサル…。これを毎週、30分番組でやっているんです。
もちろん、お金もかかります。
この50年、オイルショックだって、湾岸戦争だって、リーマンショックだってあったんです。原油をめぐるアレコレがあったんです。でも出光興産は、『題名のない音楽会』を続けてきたんです。
出光興産のサイトには『題名のない音楽会』についてのページがあります。
「題名のない音楽会」は、1964年に放送開始と歴史があり、日曜の朝に全国へ音楽の魅力や楽しさを伝えている番組です。
番組は40年以上に亘って当社が一社提供を続けていることでもよく知られています。
番組では本格的なクラシック音楽から、多彩なゲストによる演奏、ジャンルを越えたコラボレーション等にもチャレンジしています。また、公開収録で多くの方に気軽に生の音楽を聴く機会を提供しています。
当社は出光音楽賞や本番組を通じて、日本の音楽文化発展に貢献したいと考えています。
題名のない音楽会 – 出光興産
これが「真面目」なお金の使い道なんだ、と思うんです。
日本に石油を輸入するために、イギリス海軍の海上封鎖を突破してイランに入港した、出光興産のタンカー。『海賊とよばれた男』たちは、今も文化を守り続けています。
最近では、アベノミクスだ、デフレ脱却だ、と景気回復に向けて経済を動かそうとしています。
でも、景気が良くなって、お金が儲かって、その先どうするのか。お金を何に使うのか。
「真面目」に考えることって、大事なんじゃないかと思うのです。